社会保険の加入条件とは?基準や手続き、メリットまで詳しく解説
目次
企業は、従業員がどのような条件を満たせば社会保険への加入が必要となるかを正確に把握しておく必要があります。しかし、実際には手続き方法や加入基準が不明確で、対応に迷う企業も少なくありません。
本記事では、社会保険の基本的な仕組みから加入条件、トラブルを回避するための重要なポイントまで解説します。社会保険への理解を深め、適切な対応を行えるようになることを目的としています。
社会保険手続き業務の代行をご検討の方は以下のページをご覧ください。
社会保険手続き代行・アウトソーシングサービスはこちら
社会保険とは
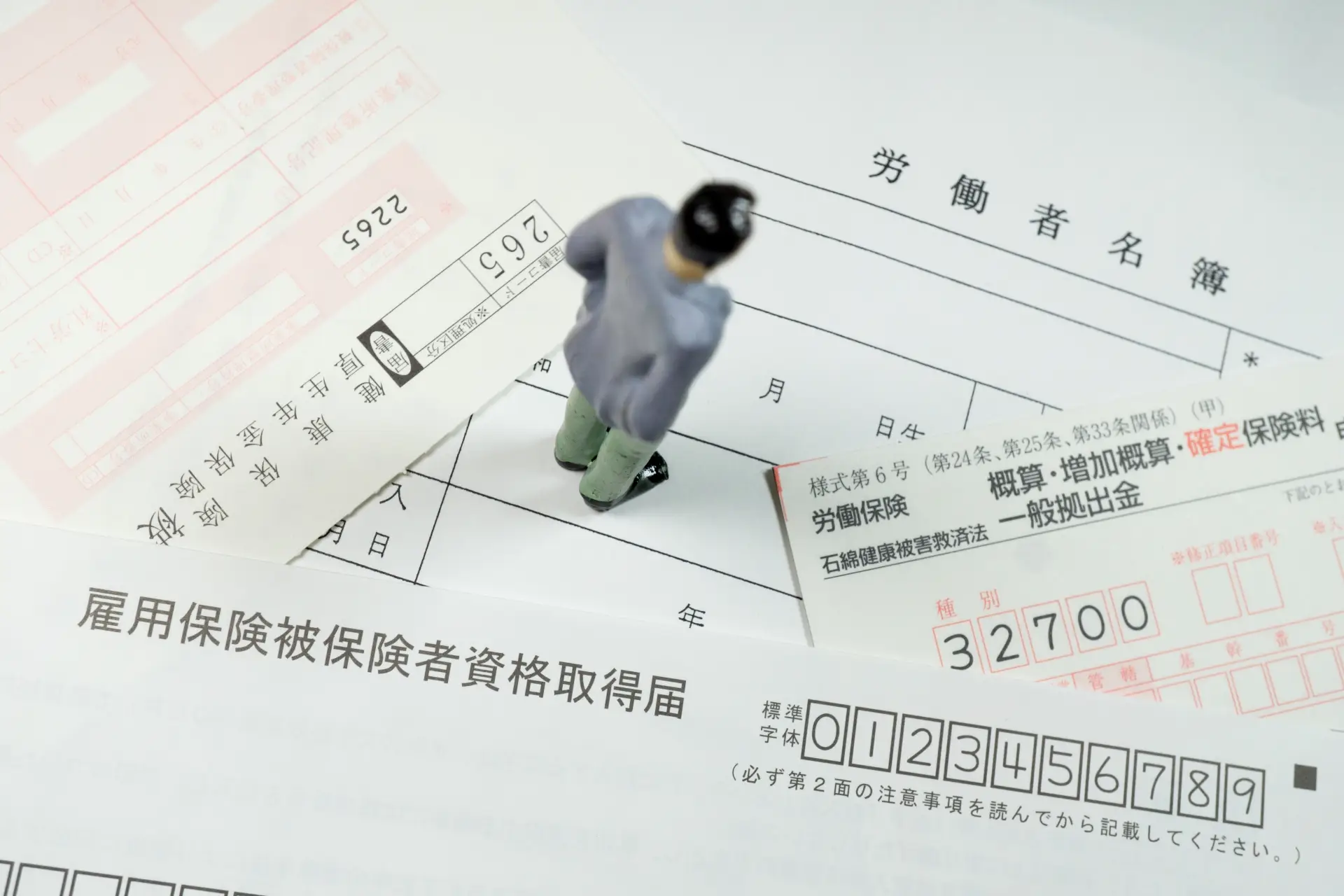
社会保険とは、病気やケガ、失業、老後などのリスクに備えるために設けられた公的制度です。
会社員は健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などに一定の条件を満たすことで自動的に加入します。各保険の保障内容は異なり、企業はその仕組みを正確に理解しておく必要があります。
社会保険手続きに誤りがあれば、従業員の信頼を損なう可能性があります。正しく加入することで従業員の安心感や信頼性が向上します。
社会保険の内訳
社会保険は、健康保険、介護保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険といった5つの保険制度によって構成されています。
従業員の雇用形態や年齢、働き方などによって適用される保険の種類が変わるため、それぞれの保険の内容と目的を知っておくことが欠かせません。ここでは、5つの制度について紹介していきます。
健康保険
健康保険は、従業員とその家族が病気やケガをした際の医療費負担を抑えるための制度です。企業と従業員が原則として半分ずつ健康保険料を負担することになります。
【計算方法】
健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率
病院や診療所で診察や治療を受けると費用がかかりますが、健康保険に加入していれば医療費の自己負担は原則3割で済みます。窓口での自己負担の割合を抑えるためにも欠かせない保険といえるでしょう。
仮に健康保険が使えない方は、かかった費用を全額自分で支払わなければなりません。また、入院や長期療養が必要な場合には、高額療養費制度と呼ばれるものが用意されています。これは、同じ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分があとから払い戻される制度です。
あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合は、限度額適用認定証を提出することで限度額を超える支払いが免除される制度もあります。それから、業務外での病気やケガによって働けなくなった場合には、傷病手当金が支給される制度も用意されています。
ここからわかるように、健康保険は従業員の生活を直接的に支える重要な制度です。
介護保険
介護保険は、将来的に介護が必要になった際にサービスを受けるための制度です。
【計算方法】
介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率
40歳以上のすべての人が加入することになっており、対象となる方は健康保険料と共に介護保険料を支払います。原則として、64歳以下の方は給与から介護保険料が差し引かれますが、65歳以上の方は居住している市区町村への直接納付です。
介護保険に加入していると、日常生活で支援が必要な「要支援状態」や「要介護状態」と認定された場合、訪問介護やデイサービス、施設入所などの介護サービスの自己負担割合を抑えることができます。
厚生年金保険
厚生年金保険とは、将来の老後資金だけでなく、万が一の際の生活保障も担う保険制度です。国民年金に上乗せされる形で「厚生年金」が支給されます。会社員や公務員が加入する年金制度です。企業と従業員が半分ずつ厚生年金保険料を負担します。
【計算方法】
厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料率
老後の生活資金としての年金のほか、障害を負った場合に受け取れる「障害年金」や、亡くなった場合に遺族に支給される「遺族年金」もあります。保険料は標準報酬月額と標準賞与額によって変わり、支払った保険料に応じて将来受け取れる年金額が増える仕組みです。
労災保険
労災保険は、勤務中や通勤中に起こったケガ・病気に対して保障を行う制度です。一部適用除外はありますが、基本的に労働者を1人でも使用している事業主は法人・個人を問わず強制的に加入対象となります。保険料は全額事業主による負担です。
【計算方法】
労災保険料=全従業員の年度内の賃金総額×労災保険率
年齢や雇用形態に関係なく適用されるため、学生アルバイトやパートタイマー、外国人労働者などにも適用されます。
雇用保険
雇用保険は、失業した場合の生活を支えたり、育児や介護と仕事の両立を助けたりするための保険制度です。代表的な給付としては、失業時に受け取る「求職者給付(失業手当)」が挙げられます。
求職者給付では、基本手当を受給しながら再就職を目指します。基本手当を受給できる日数は、離職時の年齢や雇用保険の加入期間、離職の理由などによって変わるので、事前に確認しておきましょう。
雇用保険では、求職者給付以外にも、離職後に再就職した際に給付される就職促進給付や、労働者のスキルアップを支援する給付、働き続けられるように援助するための給付などがあります。また、育児休業中の生活を支えるための育児休業給付金や、要介護状態の家族を支えるために介護休業を取得した労働者に支給される介護休業給付金など、さまざまなライフイベントに対応した給付が用意されているのも特徴です。
なお、すべての従業員が雇用保険の加入対象となるわけではありません。1週間に20時間以上働き、かつ31日以上継続して雇用される従業員が対象となります。保険料は労働者自身と事業主が負担しますが、負担割合は以下のように異なるのでよく確認しておきましょう。
事業の種類/負担者 | ①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+②雇用保険料率 |
一般の事業 | 5.5/1,000 | 9/1,000 | 14.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6.5/1,000 | 10/1,000 | 16.5/1,000 |
建設の事業 | 6.5/1,000 | 11/1,000 | 17.5/1,000 |
参考:(PDF)厚生労働省:事業主・被保険者の皆さまへ 令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内[PDF]
社会保険の加入条件

社会保険には加入条件が定められています。事業主は、どの従業員をいつ、どの保険に加入させるべきかを正しく判断しなければなりません。事業所の規模や業種、従業員の働き方や労働時間など、さまざまな条件が関係します。
判断を誤って従業員を未加入のままにしてしまうと、後々大きな問題につながることもあるため、十分注意しましょう。
※以降の内容は、健康保険・介護保険・厚生年金保険の3つの保険制度を「社会保険」とし、雇用保険及び労災保険の「労働保険」とは区分していますので、ご注意ください。
【従業員の社会保険の加入条件】
- 常時雇用されている
- 週の所定労働時間および月の所定労働日数が、常時雇用されている従業員の4分の3以上である
「常時雇用されている従業員の4分の3以上」については、通常の労働者である企業内の正社員の労働条件を基準として判断することになります。該当従業員の1週間あたりの所定労働時間と1か月あたりの所定労働日数が、同じ事業所で正社員として働いている従業員のおおむね4分の3(75%)以上に該当するか確認しましょう。
ただし、所定労働時間や所定労働日数が正社員の4分の3未満であっても例外があります。パートタイマーやアルバイトなどの非正規雇用の従業員が、以下の条件をすべて満たしている場合は、正社員と同様に社会保険への加入が必要です。
【パート・アルバイトの社会保険の加入条件】
- 週の勤務時間が20時間以上
- 給与が月額88,000円以上
- 2か月を超えて雇用が見込まれる
- 学生ではない
- 従業員51人以上の企業である
参考:政府広報オンライン:パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。
なお、雇用保険については週20時間以上の労働時間があれば原則加入が必要です。労災保険に関しては、従業員を1人でも雇用すれば、業種にかかわらず原則として強制適用となります。
このように、保険の種類ごとに加入条件や適用基準が異なるため、正確に理解しておくことが重要です。加入すべき従業員を加入させていなかった場合、多額の保険料を追徴される恐れもあります。社会保険の制度はたびたび見直しが行われているため、最新の情報に注意し、適切に対応しましょう。
社会保険に加入する従業員側のメリット
社会保険に加入することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。事業主にとっては負担が増える一方、従業員にとっては将来の安心や生活の安定を得られることが大きなメリットです。
社会保険に加入していることで得られるメリットは、老後だけにとどまりません。病気やケガなどが生じた際の生活保障や、医療・育児・介護などのライフステージに応じた支援も受けられます。
ここでは、社会保険に加入することで得られる従業員側の代表的なメリットを4つ紹介します。
将来的に受け取れる年金が増える
厚生年金に加入している場合、国民年金と比べて将来受け取れる年金額が増えます。これは、国民年金で受け取れる老齢基礎年金に加えて、老齢厚生年金が支給されるためです。
老後の生活にゆとりをもたらす重要なポイントといえます。特に若い世代では「将来の年金額には期待できない」と考える人も多くいますが、厚生年金による年金の上乗せは大きな魅力です。
日本は長寿国として知られており、将来の生活費に不安を感じる人も少なくありません。年金は終身で支給されるため、老後資金の大きな柱となります。 厚生年金は加入期間と収入に応じて支給額が増える仕組みです。企業としては、長く加入することで受給額が増えることを従業員に理解してもらう取り組みも大切です。
障害がある状態になった場合の保険になる
人生いつ何が起こるかわからないため、突然の病気やケガによって障害を負ってしまう恐れがあります。国民年金に加入している場合は障害基礎年金が支給されますが、社会保険(厚生年金)に加入していれば、障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受け取れるのが大きなメリットです。
障害年金は、病気やケガが原因で日常生活または仕事が制限される状態になった場合に受給できる年金のことをいいます。 年金といえば、高齢期の生活を保障する老齢年金が一般的に知られていますが、障害年金については高齢者のみを対象としたものではありません。
将来を見据えたとき、健康状態の変化は誰に起こってもおかしくないため、社会保険に加入することはリスクに備えるうえでもメリットがあります。自分の体に万が一のことがあっても、保険制度が生活を支えてくれます。
医療保険が充実する
健康保険に加入していれば、医療費の自己負担が軽減されることに加え、家族も手厚い保障を受けられるのが特徴です。医療費の自己負担が原則として3割で済むほか、入院や手術などの高額な治療が必要になった場合は高額療養費制度で1か月あたりの自己負担額に上限が設定されます。
社会保険に加入することで傷病手当金や出産手当金の対象となるため、従業員だけでなく、家族の安心にもつながるでしょう。
保険料の半分を事業者が負担する
国民健康保険では、被保険者本人が保険料を全額負担しますが、社会保険では会社と従業員が保険料を原則として半分ずつ負担します。これは従業員にとって大きなメリットです。
個人事業主やフリーランスが全額自己負担で加入する場合と比べて、負担が大幅に軽減されます。そのため、社会保険に加入できる職場は従業員にとって魅力的な雇用条件となります。
社会保険の適用対象となる事業所
社会保険の適用対象となるかどうかは、事業所の業種や規模によって変わります。そのため、すべての事業所が同じ条件下で社会保険に加入しなければならないわけではありません。
事業所の種類によって「強制適用事業所」か「任意適用事業所」に分かれており、それぞれで加入義務の有無や手続き内容が異なります。この区分を正しく理解せずに放置すると、トラブルにつながる恐れがあるので注意しましょう。
ここでは、強制的に加入が必要な強制適用事業所と、任意適用事業所についてそれぞれ解説します。
強制適用事業所
以下に該当する事業所は、社会保険への加入が強制される「強制適用事業所」に該当します。
【強制適用事業所に該当する条件】
- 従業員が1人以上いるすべての法人事業所
- 常に従業員を5人以上雇用している個人事業所
法律によって社会保険への加入が義務づけられている事業所でもあります。法人については、たとえ社長1人しかいない状態でも手続きが必要です。特に個人事業主や小規模な法人では、「自社の規模が小さいため社会保険の対象外」と誤解されることがあります。しかし、条件を満たしていれば必須であるため、正しく判断しましょう。
なお、個人事業所については、法律で定める17業種(※1)以外の農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業などに関しては現在対象外です。ただし、2029年10月から対象となる点に注意しておきましょう。(※2) 5人未満の個人事業所については対象外とされています。
加入義務を怠った場合は、後から保険料や延滞金をまとめて支払わなければならないケースがあるため、よく確認が必要です。
(※1)参考:(PDF)厚生労働省:個人事業所に係る適用範囲の在り方について[PDF]
(※2)参考:厚生労働省:社会保険の加入対象の拡大について
任意適用事業所
任意適用事業所とは、社会保険への加入が法律で義務付けられてはいないものの、希望すれば任意での加入が認められている事業所のことをいいます。以下に該当する場合は一定の条件を満たすことで社会保険の任意加入が可能です。
【任意適用事業所に該当する条件】
- 従業員が5人未満の個人事業所
- 非適用業種
社会保険に加入するとなれば従業員は社会保険料を支払う必要がありますが、任意適用事業所でも社会保険に加入することで大きなメリットがあります。
社会保険に加入することで、従業員は老後や病気・ケガへの備えが手厚くなり、安心して働けます。そのため、事前に丁寧な説明を行い、従業員の理解と同意を得ることが大切です。
また、企業側にとっても雇用の安定性が高まり、求人への応募が増えることが期待できるでしょう。
事業所が社会保険の加入条件を満たしたときに行う手続き

事業所が社会保険の加入条件を満たした場合は、速やかに手続きを行う必要があります。条件を満たした後、好きなタイミングで加入できるわけではなく、一定の条件を満たした時点で加入義務が発生します。
手続きを怠ると、保険料の追徴や行政指導を受ける可能性があるため、十分注意しましょう。ここでは、社会保険の適用対象となった時に必要な3つの手続きについて解説します。
適用事業所になるための手続き
強制適用事業所ではない任意適用事業所が適用事業所として認められるためには、手続きが必要です。 会社側が独自に決定することはできず、従業員の半数以上から適用事業所となることについて同意を得ていなければなりません。
そのうえで、速やかに事務センターまたは管轄の年金事務所まで電子申請・郵送・窓口持参のいずれかの方法により申請書を提出します。承認されれば、以後は強制適用事業所と同様に保険料を支払い、各種給付の対象となる形です。
従業員の社会保険加入手続き
従業員が社会保険の加入条件を満たした場合は、事業主側が速やかに加入手続きを行いましょう。手続きをするのは従業員本人ではなく、事業主側です。年金事務所に対し「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。
添付する書類はありませんが、加入対象となった時から5日以内に提出しなければなりません。なお、健康保険組合に加入している場合は健康保険組合での手続きが必要となります。
従業員の家族を扶養に入れる手続き
家族を扶養に入れることで、その家族も医療費の軽減や各種給付の対象となります。ただし、自動的に扶養になるわけではなく、従業員の家族を扶養に入れる際は、戸籍謄本や住民票、所得証明などの書類を添付して、加入している健康保険組合などに申請しなければなりません。
なお、扶養に入れた後も、収入の変動などによって扶養から外れる場合があります。変更があった場合は、速やかに「被扶養者(異動)届」を提出し、適切に対応しましょう。
関連記事:社会保険手続きを業務委託するメリットと注意しておきたいポイント
社会保険に関する必要な手続きを行わなかった場合の罰則
社会保険の手続きを怠った場合は、行政からの指導や罰則、追徴金などの厳しい対応を受けることになります。具体的にどのような罰則が用意されているのか確認しておきましょう。
日本年金機構からの指導が入る
社会保険の加入対象者が未加入だった場合は、日本年金機構から加入状況に関する調査が入ることになります。日本年金機構から案内文書が届いた場合は、内容をよく確認し、正しく対応しましょう。
必要に応じて実地調査や加入指導が行われることもあります。 大事にしないためには、速やかな対応が必要です。
罰金や罰則が科せられる
悪質な対応や虚偽申請を行った場合、罰則が科せられる可能性があります。健康保険法の違反となり、科せられるのは6か月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金です。
業界紙や報道などで罰金や罰則が科せられたことが取り上げられた場合、社会的な信用を失う可能性もあります。行政指導には正しく対応することが重要です。
未納分を徴収される
加入義務があるのに放置していた場合でも、未加入期間の保険料が免除されることはありません。未加入だった期間についても、保険料の納付義務が発生します。
過去2年間にさかのぼって納付が必要です。これは現職者だけではなく退職者も対象となるため、注意が必要です。従業員負担分を後から徴収する場合、雇用関係のトラブルにつながる可能性もあります。
ハローワークに求人を掲載できなくなる
社会保険に加入しなければならないのに未加入の場合、ハローワークでの求人掲載ができなくなります。採用活動でハローワークを中心とした求人を行っている場合、大きなマイナスになってしまうはずです。
経営課題につながりかねないので、人材確保の観点からも、社会保険への加入が求められる場合には、速やかに対応する必要があります。
社会保険制度への正しい理解と適切な対応が重要
ここまで、社会保険の加入条件やメリットなどについて解説しました。企業側は各社会保険について正しく理解し、適切に対応することが重要です。
不明点や対応に迷う場合は、専門家である社会保険労務士などに相談し、正確な知識と対応力を身につけましょう。 社会保険労務士法人エスネットワークスでは、社会保険に関する手続きの代行も行っています。
専門的な知識に基づき、正しい書類の作成や届け出をサポートしているので、法令遵守に取り組みたい場合はぜひご相談ください。社会保険関係の手続きに定型業務に多くの時間を割かれており、コア業務に集中できないといった場合も業務効率化と時間創出につながります。
【サービス一覧】
給与計算アウトソーシング・代行
社会保険手続き代行
年末調整補助アウトソーシング
労務デューデリジェンス
労務顧問サービス
就業規則・賃金規程の作成
ハラスメント防止研修
助成金コンサルティング

